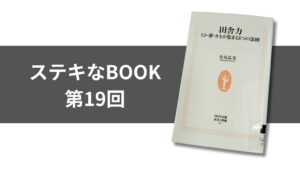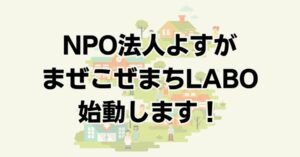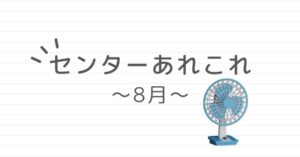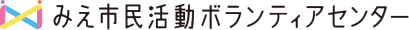目と目をあわす。一人ひとりを大切にする。
湯浅 しおり氏(NPO法人あいあい 理事長)

森と海に囲まれた尾鷲市。NPO法人あいあい理事長の湯浅しおりさんは、株式会社OCK Ba-mi、一般社団法人おもてなしと次々と組織を立ち上げ、地域の困りごとを解決する事業を展開。女性3名で立ち上げた事業も今では180名。ディサービス、ショートスティ、災害避難施設を兼ねた7階建ての介護・障害者施設を建設。さらには、尾鷲観光物産協会の代表理事に就任し、三重県立熊野古道センターに隣接する「夢古道おわせ」を営業しています。
尾鷲にて…
神奈川県で生まれたのですが、家庭の事情で母と姉と3人で母の実家である尾鷲に引っ越しをしました。小学校5年生から中学3年生まで尾鷲で暮らし、その後名古屋の看護学校に進学、卒業し、准看護師になって19歳で尾鷲に戻りました。個人の産婦人科の病院で働いていましたが、すぐに結婚。子どもを2人産み、その後は夫の父親が肺気腫のため、同居しながら、地域の開業医で働き、亡くなった後も10年間勤めましたが、何か違うことにトライしたいという気持ちが高まっていました。
そんな時に、尾鷲で大手介護サービス企業が営業をすることになったという話を聞きました。准看護師も就職できるということを聞いて、その会社に連絡をしました。とても対応がよく、接遇にもひかれて面接に行きました。私は新しいことをしたい気持ちが強く、病院を辞め、義父の介護経験もあったことから採用されました。しかし、田舎はとても閉鎖的で、新たな民間企業の参入は厳しかった。営業に行っても門前払い。365日24時間訪問介護をする企業がなぜ受け入れられないのかを聞いてみると、「大手会社の名前ではなく、湯浅しおりの名前で仕事をした方がよい」とアドバイスを受け、その頃、会社には3人スタッフがいましたが、スタッフと病院で働いていた頃の患者さんにハガキを送りました。そうしたら、「困っているんだ。しおりちゃん来てほしい」と依頼が来るようになりました。
営業が楽しく、尾鷲中を歩き回り、営業をする毎日。そんな私の姿を見ていた友人が「しおりさんの動きは社長だよ。訪問介護事業をするには法人格が必要だから会社をつくって自分がやったほうがいいよ。」と言われました。2人の仲間に相談をしたら、「あんたについていくからあんたが決めて」と言われ、「この2人の雇用の責任を果たしたい。3人のメンバーのうち私を含め2人が母子家庭、だからこそなんとかしないといけない」と考えました。その時、私は33歳でした。
法人格を取得しようと思い、株式会社や有限会社を調べると費用がかかることがわかりました。費用がかからないのがNPO法人でした。その頃スタートしたばかりで、NPO法人の取得は県から職員が来て一生懸命に指導してくれました。書類作成が得意なメンバーがいて、彼女がすべて作成し申請をしました。
NPO法人あいあい スタート
2000年12月、NPO法人あいあいがスタートしました。半年で立ち上げ、3名の給料が出せるようになりました。給料を出すので精一杯。素敵な事務所なんていらない。自分の車を使い、制服も自分で買って揃えました。でも、どうしても「365日24時間の介護・看護」という看板だけは守りたくて、依頼を頂いた方はすべて訪問しました。
お客さんが増えていくと、あいあいを利用している方は他の施設を一切使えなくなりました。訪問介護を利用してくださる方がデイサービスに行きたいと言っても問い合わせると全部断られました。しかし、こんなことでは凹みませんでした。この状況を面白いと思いました。お客さんの利益は「絶対」です。「あいあいを利用するのを止めて他の施設を利用すればデイサービスに行けるから」とおばあちゃんに言うと「負けるな」と怒られました。でも「勝つとか負けるとかではなく、みなさんの利益しか考えていない」と伝えていました。そんな私たちの考え方に共感してくれる人たちがいてくださる。自分たちで古い家を改装してデイサービスを始めました。今考えたら、すべてほかの事業さんと共存できていたら、あいあいの拡大はなかったように思えます。


みんなでつくったお母さんが働く環境
一番やりたかったことは、「小さな子どもをもつお母さんが働いてくれる職場にすること」です。私自身が辛い経験をしているからです。子守りをしてくれる人がいなかった。子どもが病気になったら休まなければいけない。お父さんの介護で休まなければいけない。頑張りたい自分と、休みを取らなくてはならない環境との板挟みで悩みました。そこで「魅力ある職場づくり」のテーマとして「お母さん、みんなおいで。子ども連れで出勤してもいい。子どもの体調が悪い時は休んで。みんなが協力するから安心していいよ」そんな職場にしました。「みんな」というのはお客さんも含まれます。「あの子の子ども、熱があるんだったら今日のごはんはいいわ」と言うおばちゃんがいる。「私が弁当を買ってくるわ」となる。お客さんの協力がとても温かい。「子どもの運動会に行けない」とスタッフが言うと、「私らが弁当配るよ」「掃除は明日に延ばしていいよ」と言ってくれる。利用者のみなさんと今の状況を築きあげました。応援団が増えました。
私たちが大切にしたことはサービスを利用いただく方への感謝、「ありがとう」の気持ちです。夜中のケアサービスも依頼が多くなりました。ショートスティをしてほしいという依頼もあり、ショートスティも始めました。

必然性とつながりが生み出す多様な事業
13年目くらいで経営が悪化しました。前を向いて走りすぎて、振り向いて現状をしっかり把握していなかった。銀行に調べていただくと大変な経営状況になっていました。すぐに見直しをかけて、訪問介護、デイサービスなど経営がうまくまわる仕事量、仕事バランスに改善しました。食事づくりを7つの厨房でしていましたが、1つにして、新しい厨房を建て、2018年に飲食部門を担う株式会社OCK Ba-miを設立しました。
その後、2018年6月に津駅前に「橙々屋(だいだいや)」といううどん店をオープン。そして、津市にある県の総合文化センター内で、障害者の雇用推進を目的にしたステップアップカフェ「だいだい食堂」を2024年12月まで営業しました。閉店したのは、働いていた障害者の方が新しい職先に就くなど就労支援の役割をある程度終えたと判断したからです。

さらに長男が「お母さん、仕事をやめてラーメン屋をしたい」と言い出し、「橙々屋」の場所が空いていて調理機材も全部置いてあったので、そのまま利用し、ラーメン屋「喜鷲(きしゅう)」をオープンしました。
7年間の津市での仕事を終え、昨年12月には尾鷲に戻りました。その7年間でスタッフの自立、成長を目の当たりにし、私がいなくても現場の業務がまわっていました。
そんな時、尾鷲市の観光物産協会の理事長になってほしいという依頼が舞い込んできました。尾鷲市のホテル利用が少なく、観光客があまりいない。任期が2年間と聞き、やってみようと思いました。ホテル業も始めました。ホテルを経営していた友人が手放すことになったため購入しました。観光業を盛り上げるための策です。そして、観光の拠点がないと気づきました。「夢古道おわせ」が観光物産協会のものだったらな、と思っていました。そんな時に「夢古道おわせ」の指定管理者募集が始まった。一般社団法人おもてなしを設立し応募し、指定管理者となりました。
しばらくすると長男から連絡があり、「喜鷲の入っているビルを壊すことになったから撤退しないといけなくなった。次の場所を探さなければならない」と言う。「夢古道おわせ」でラーメンを提供することになりました。そして、尾鷲で魚料理店を経営している「ほんじつのさかな」も土・日曜日、祝日に「夢古道尾鷲」で営業をしてくれることになりました。このつながり、この必然性に私自身も驚いています。


家族ぐるみのコミュニティ

尾鷲の人口は1万6000人ぐらいです。家族ぐるみで、みんなお互いをよく知っています。私の同級生の子どもたちも尾鷲に戻ってきています。介護など専門職をもって帰ってきてくれています。あいあいは個別ケアをとても大切にしています。
1人1人に寄り添うことをスタッフに伝えています。時間がかかっても人間らしく利用者、患者さんと接することを大切にしたい。
これからも尾鷲にいます。責任を果たさないといけない。人が集まることのできるコミュニティを作らないといけない、そのためには場所を開放できる人が必要です。いつでもだれでもウェルカムな場所が必要だと思っています。私の自宅がその役割を担っています。公民館的な場所。みんなが集まり、使い、食事を一緒に食べ、話をする場所です。
私のこと
健康には気をつけています。20:30~21:00には寝て、朝の4時半に置きます。夕飯は17:00~20:30。寝るのが大好きで睡眠はしっかりとっています。私の仕事のほとんどは相談業務です。疲れていたり、不眠の状況だと相談された時に面倒だと感じてしまうかもしれません。相談にはいつでものりたいという気持ちでいるので、いつも心と頭を空にするために前の日の問題は前の日のうちに解決します。明日相談したい、は禁止にしています。明日は明日の問題がありますから。
食べものはとても健康志向です。玄米食べたり、発酵食品を食べたり。ラーメンも大好きですけど麺は半分、スープ飲まない。気をつけられることは気をつけます。お酒は毎晩飲みます。朝食は絶対食べます。食べないのは健康診断の1年に1回だけ。味噌汁と納豆とご飯と自分のぬか漬けをいただきます。
私の強みは、「母親が破天荒で彼女の人生に振り回されたことによる強さ」だと思っています。子どもは弱者だから大人がいないと生きていけない。だから反抗もしなかった。それを感じて生きてきた。今では、母親の生き方を学べたことに感謝をしています。

あいあいへの思い
あいあいを始める時に覚悟があったかとよく聞かれますが、逆に覚悟がないからできたと思っています。会社をよく知らなかった、わからなかったからできた。車1台持つのも100台持つのも責任は一緒です。1人雇用するのと250人雇用する責任は一緒です。1人を雇うか雇わないかです。やるかやらないかの覚悟だけです。いろいろありましたが、その都度逃げずに向き合ってきました。それが一番だったと思います。それを必然と思う前向きさがあったからできた。いつも自分が責任をとるんだと思っていたら楽に生きられます。誰かのせいに、何かのせいにしたら、その方がつまずくし、苦しいです。どうして私の人生はこんなんなんだろう、何か悪いことしたんだろうか、と思う時もありました。でも考え方が変わりました。自信がついたのでしょうか。自分が間違っていないことを認識できました。
看護師の時から患者さんに背中で返事をしてはいけない、と心がけていました。呼ばれたら必ず振り向く。それが1番大事だと看護師の時から気づいていて、患者さんだけでなく子どもも同じです。目を見て話す、目と目はすごく大事だと。だから、eye2(あいあい)。子どもがいつも「アイアイ♪」って歌っていたこともあるかな。